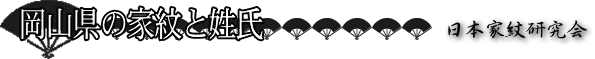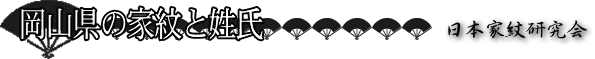|
■岡山県の家紋
岡山県は北を中国山地、南を瀬戸内海に囲まれ、自然災害が少なく気候が温暖で、古くから吉備国として栄えていた。
歴史をさかのぼってみると、江戸時代以前は、岡山県内の家紋はそれほど種類が多くはなかったであろう。
江戸時代になって岡山に移ってきた諸大名は城下町開発のために武士以外にも多くの民をひきつれて来ており、それまで岡山に存在しなかったような家紋がこのときに移動したと思われる。加えて、倉敷、笹岡などの天領(幕府直轄地)は、人の往来がさかんだったため、周辺の村に比べて家紋の種類が多い。
家紋の隆盛を見る江戸時代には、備前、備中、美作の3国に分かれていたため、分布状況にもその影響が出ている。個別の事例を挙げると、
(1)美作国の武士団美作管家党の梅鉢紋は拠点となっていた勝田郡、津山市や英田郡では頻繁にみられ、子孫が移り住んでいる岡山市でも観察されるが倉敷市では管家党の梅鉢紋はあまり見られない。
(2)稲妻紋は備中国岡田藩大名家で使われていた為、岡田藩周辺では使用が憚られたとおもわれるが、旧備前国内では、他の名字の家での使用が散見される。
(3)五つ瓜の中に他の紋を入れた合成紋は、人口比率を考慮すると旧美作国での使用がすこぶる多い。
(4)備前国岡山藩大名家の池田氏の揚羽蝶紋は、備中国の池田氏や美作国の池田氏でも使用されており、阿哲郡では浮線蝶紋や対い蝶紋を使用している池田氏も存在する、などの特徴がある。
一般に知られている佐々木氏族の目結紋、渡辺氏族の渡辺星紋などは県内全域に分布しルーツの説明もつくが、他の姓氏については、同じ村内でも数種類の紋が使われていたり県内での人口ランキングの上位姓では、1種類の名字につき10〜20種類以上の家紋が使用されているなど、全国的な尺度がそのままではあてはまらないケースも多数ある。
家紋の連続性については、明治時代以前の史書・古文書に記述された家紋を伝統を守って伝えている家もあれば、何らかの理由で途中で変更している家もある。
■岡山県の10大家紋
現在までの調査では木瓜、藤、片喰、桐、梅鉢、鷹の羽、茗荷、蔦、菱、柏の各紋が多く見られた。
このうち、他の家紋との合成により次々とバリエーションが増えているのは木瓜、藤、菱紋の3種類である。
これらを除けば、実質的には片喰紋が1番である。
桐紋は、既に『日本家紋総鑑』において岡山市、倉敷市、玉野市など岡山県南部で多く分布していることが指摘されているが、なぜ多いのかについての理由ははっきりしていない。武士の代表的な下腸紋なので、あこがれて使用しているのか、あるいは瀬戸内海沿岸地域で広範囲に流行した女紋からの転用かとも推定される。
梅鉢紋は、美作国に勢力を保っていた美作管家党の代表紋であり、現在までに派生して88家とも言われている子孫は、ほとんどがこの紋を伝えており党族の紐帯がいかに強力であったかを如実に示している。
鷹の羽紋は、荒神様の信仰の厚かった美作国を中心に県内全域で見られ、茗荷紋とセットで使用している氏も散見される。
蔦紋は、揚羽蝶紋、桐紋とならぶ代表的な女紋であり、蔦の繁殖力の高さから、子孫繁栄を願って使用したものであろう。
以上は、日本家紋研究会関西支部の調査である。 |
岡山県の家紋調査姓氏数
総数 3,500姓氏 |
|
|