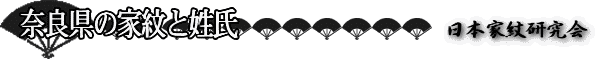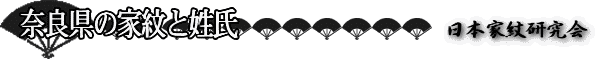奈良県の代表的家紋
(1)片喰紋(かたばみ) |
 |
|
 |
| 丸に片喰 |
|
丸に剣片喰 |
|
カタバミは酢漿草、鳩酸草とも書くが現在は片喰が用いられる。片喰はカタバミ科の多年草で、クローバともいわれる。庭、路傍などに自生し茎は地面を這う。葉はハート形をしており、三枚で春から秋にかけて黄色の小さな花をつける。繁殖力が極めて旺盛で、噛むと酸味が強いので酢漿草と書かれた。
家紋として用いられたのは、その旺盛な繁殖力を家運にかけて用いられたといわれるが、これは後講釈と思われる。家紋として史籍に現れるのは、平安時代に車の文様として見られたことが〔続世継〕に載っている。次第にこの文様は家紋に移行して、南北朝時代には源氏の新田氏の配下の士が用いたと〔太平記〕に記されている。以降この片喰紋は公家、大名家なども多く用い、幕臣では160余家が用いて我が国の代表的な家紋となった。
奈良県においても使用家はだんとつで一位であり、他の家紋を引き離している。片喰紋より剣片喰紋の方がはるかに多い。
|
| (2)橘紋 |
|
|
橘紋は大和国とは古代から縁が深く、他県に比して多く使用されている。橘はミカン科の常緑小高木で、我が国原産の唯一の柑橘類といわれる。初夏に芳香のある白色の五弁が開く。橘紋はこの橘を象どったものである。
古伝によると垂仁天皇はタ遅摩毛理〔タジマモリ〕を常世〔トコヨ〕の国に遣わして、珍しい美果を求められた。その美果が橘といわれる。橘の名はその伝来者であるタ遅摩毛理にちなんで名づけられたものである。タ遅摩花から転訛したといわれる。
橘はこのような故事にのっとり、当時は最高の果実といわれ、万葉集にも数多く詠まれている。
橘は時代とともに橘氏族の家紋として定着していった。また藤原氏にも橘紋を用いる氏も多い。家紋として初めて史籍に現れるのは足利時代の〔見聞諸家紋〕であり、次第に使用家が増えて、幕臣では100余家が用いている。現在も我が国の十大家紋の一つである。分布としては、奈良、大阪、など関西地方に多い。 |
|